





スマートフォン『Xperia 1 VI』
「Xperia」はソニーが誇る、カメラやテレビ、スピーカーなどの高機能を貪欲に取り込むことで、その魅力を高めてきました。ここではその最新フラッグシップモデル『Xperia 1 VI』の開発当時を、Xperiaのエンジニアとその開発に協力した各製品ジャンルのエンジニアたちが振り返りながら、製品に凝縮された“ソニー”の技術とこだわりを語り尽くします。
Index

α × Xperia
『Xperia 1 VI』は
「スマートフォンの皮を被ったα」だ

「美の真実」を追求した
カメラとスマートフォン
美しさは被写体そのものにある。それを何よりも大切にするのがソニーの哲学のひとつ。強調しすぎない、素材を活かした自然な画質、そして人の記憶に忠実に美しく再現することは「α」と「Xperia」共通の思想だ。まずは身近な人の肌の色を見比べてみてほしい。


目指したのはαユーザーの
「ポケットに入るα」
これほどのスリムボディにあらゆる被写体に相対できる超広角(16mm相当)、広角(24mm・48mm相当)、望遠ズーム(85〜170mm相当)の大口径トリプルレンズを搭載。撮影機能や操作性も、手に馴染んだ「α」そのままを追求しているから、「α」のサブカメラとして違和感なく併用できる。


-
![[α]カメラ画質設計担当 玉木](./page_assets/images/icon_tamaki.png?rel20240607)
[α]
カメラ画質設計担当
玉木 「α」で3本ものレンズを持ち運ぶときは、その日に撮影する気持ちがあって、きちんと準備しているケースがほとんどですよね。一方、常にポケットに入っていて、とっさに撮影したい場合にも満足いく写真が撮れるのはスマートフォンならではのアドバンテージだと思っています。
『Xperia 1 VI』のカメラで何を撮りたい?

BRAVIA × Xperia
「ブラビアの感動」を
リビングから持ち出す

最高の映像美は“記憶”の中にある
受け取った映像をただそのまま再現するだけでは、人の心を震わせることはできない。「ブラビア」では、そうした映像のコントラストや質感、発色などを大きく高め、記憶の中のイメージを再現することで、その時、その場の“感動”を視聴者へと届ける。「Xperia」が目指したのは、その感動を手のひらのディスプレイでも再現できるようにすること。

-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 「Xperia」は10年以上前から「ブラビア」画質の再現を追求してきましたが、今回、改めて最新の「ブラビア」画質を「Xperia」に取り込むことで、この10年で最高の画質向上を実現することができました。

『Xperia 1 VI』なら「ブラビア画質」を
空の下でも楽しめる
自宅だけでなく、屋外のさまざまな場所で使うスマートフォンでは、どのような環境でもしっかり映像を楽しめるようにする仕組みが必要だ。『Xperia 1 VI』は、真夏の直射日光下でもしっかり見える高輝度ディスプレイに加え、映像の美しさを確保する新機能「サンライトビジョン」を搭載。表現力豊かな映像を楽しめる。

-
![[BRAVIA]テレビ画質設計担当 高橋](./page_assets/images/icon_takahashi.png?rel20240607)
[BRAVIA]
テレビ画質設計担当
高橋 「サンライトビジョン」を初めて体験したとき本当に驚かされました。こんなに眩しい場所でこれほど美しい映像を楽しめるのかって。屋外で動画を見ることが多い人にぜひ試してみていただきたいですね。
『Xperia 1 VI』でどんな映画を観たい?

Sony Audio × Xperia
こんな小さなボディにもしっかりと「ソニーの音」

ソニーの誇る
“本物の音”を手のひらに
『Xperia 1 VI』は内蔵スピーカーの臨場感、迫力を、シリーズ過去最高レベルに大きく向上。映画を観ている時にはサウンドバー『BRAVIA Theatre Bar 9』の包み込まれるような立体音響空間を、音楽を聴く時にはSignature Seriesのニアフィールドパワードスピーカー『SA-Z1』を彷彿とさせる立体的なミュージックステージを再現する。

-
![[Sony Audio]音質設計担当 加来](./page_assets/images/icon_kaku.png?rel20240607)
[Sony Audio]
音質設計担当
加来 はじめて『Xperia 1 VI』の音を聴いた時、「他人の音じゃないな」と思いました。クリエイターの思いをリスナーにそのまま伝える音作りをしていくと、いつの間にか「ソニーの音」になっていくのでしょうね。

何も足さず、何も引かない。それが
「私たちソニーの音」
長年ソニーが培ってきた、よりいっそう音楽と映画を楽しむための音作りのノウハウを『Xperia 1 VI』へと惜しげもなくつぎ込んだ。大切にしたのはダイアログ(セリフ)とボーカル。こだわったのはその音にできる限り何も足さず、何もひかないこと。クリエイターの思いをダイレクトに感じ取れる「ソニーの音」を『Xperia 1 VI』なら、どこにでも持っていける。

-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 実はアニソンってものすごくハードルの高いコンテンツなんですよ。同時に複数のトラックがものすごいスピードで音の粒をばらまく中にボーカルがいて……。その点、『Xperia 1 VI』のスピーカーなら、今どきのアニソンの複雑でハイスピードなトラックも、混濁せずに気持ちよいアンサンブルとなって楽しめます。
-
![[Sony Audio]音質設計担当 加来](./page_assets/images/icon_kaku.png?rel20240607)
[Sony Audio]
音質設計担当
加来 映画館のスクリーンと大型テレビ、そしてスマートフォンの画面では、それぞれ画面サイズが異なりますから、それに合わせた適切な音質だったり、画面と違和感のない音像のサイズだったりが映画への没入感には重要だと思います。その点、『Xperia 1 VI』は、手のひらに映画館が入っているような立体感と没入感が得られると感じます。
『Xperia 1 VI』でどんな音楽を聴きたい?

安定したハイパフォーマンスが支える
ソニークオリティ

体験を止めない。
感動を止めない
スマートフォンに求められるのは瞬間的なハイパフォーマンスよりも、ずっと快適に使い続けられること。そのために必要なのは、局所的な最適化ではなく、ハードウェアからソフトウェアまでスマートフォン全体を俯瞰したチューニング。ソニーではかねてよりシステム全体でのパフォーマンス最適化を重視しており、専任チームが全体を見ながら、スペックでは測りきれない高性能化を追求している。

-

パフォーマンス
エンジニア
春木 『Xperia 1 VI』は電力的にも構造的にも改善を入れて、「Xperia 1」シリーズとしては過去最高と断言できる放熱性能になっています。過去の製品では、お客さまから厳しい声をいただくこともありましたが、『Xperia 1 VI』では必ずやご満足いただけると自信を持っています。

「長い時間」使えるし、
「長い期間」使い続けられる
『Xperia 1 VI』はバッテリー性能にも“感動”を求めた。これまで目標としてきた「充電なしでも2日持ち」を実現したほか、これまでも好評だった「3年使い続けても劣化しにくい長寿命バッテリー」も「4年」にまで延長するなど、「Xperia」過去最高のバッテリー性能を実現している。

-

ソフトウェア
設計担当
大木 この数値を実現するべく、パフォーマンスエンジニアたちが試作機を日常の中で長期間試用し、実使用で浮かび上がってくるバッテリーを無駄に消費する要因をひとつひとつ潰していきました。本当にもうこれ以上、消費電力を最適化できないというところまで追い込んだ自負があります。
スマートフォンのバッテリーはどれくらいもってほしい?


α × Xperia

写真を知り尽くしたプロフェッショナルたちが作り込んできた、デジタル一眼カメラ「α」の画。「Xperia」のエンジニアたちは早くからそのこだわりと撮影機能をスマートフォンの世界に持ち込み、気軽に高画質で撮れることに加え、専用機ならではの“こだわって撮る楽しみ”をより多くの皆さまに提供してきました。ここではそのこだわりを、「α」と「Xperia」双方の画質設計担当者が解説します。
-
![[α]カメラ画質設計担当 玉木](./page_assets/images/icon_tamaki.png?rel20240607)
[α]
カメラ画質設計担当
玉木 -
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山
日々、進化し続けている
「α」の画作り
「α」の画質にはどんなこだわりが込められているのでしょうか?
-
![[α]カメラ画質設計担当 玉木](./page_assets/images/icon_tamaki.png?rel20240607)
[α]
カメラ画質設計担当
玉木 「α」にはこれが初めてのカメラという入門者から、カメラを仕事で使っているというプロフェッショナルまで幅広いユーザーがおり、被写体もそれぞれ大きく異なるため、かなり細かく”こだわって”います。たとえば解像感やコントラスト感を強調しすぎない、素材を活かした自然な画質はそうした“こだわり”のひとつです。そのほか、人物写真においては肌の色と質感を美しく描く事にも力を入れていますし、屋内や夜間のスポーツ撮影で使われるような中〜高感度での撮影時にはノイズと解像のバランスが取れた画作りを目指すなど、さまざまな観点から、常にユーザーの声に耳を傾けつつ画質を追い込んできました。L判からポスターなどの大判まで多彩な選択肢のあるプリント出力から、100%拡大表示ができるモニターまで、さまざまな視聴環境がある中で、どのような環境であっても自然でリアリティのある描写を目指して設計しています。

そのこだわりによって生み出される「α」の画質は全ての製品で共通しているのでしょうか?
-
![[α]カメラ画質設計担当 玉木](./page_assets/images/icon_tamaki.png?rel20240607)
[α]
カメラ画質設計担当
玉木 入門者向けのモデルとプロフェッショナル向けのモデルでは求められる画質傾向が異なりますし、それぞれハードウェアの違いもありますから、製品ごとに静止画、動画の画質を担当するチームで話し合いながら決めています。ただ、複数の「α」で同じ被写体を撮ったときに極端な違いを感じてしまうのは避けたいですから、機種間での整合性は意識して画質設計を行っています。「α」シリーズとしてのひとつの大きな柱を作って、そこに製品ごとに味付けをしていくというイメージです。
「α」としての画質があるということなんですね。
-
![[α]カメラ画質設計担当 玉木](./page_assets/images/icon_tamaki.png?rel20240607)
[α]
カメラ画質設計担当
玉木 その通りです。ただ、不変的な物もありつつもこの“柱”は必ずしも不変のものではありません。カメラに求められる画質は時代によって大きく変わっていきますし、ハードウェアもどんどん進化していきますから。定期的に最新事情に併せたアップデートを行い、中長期的な観点から「α」の画質を作り込んでいくようにしています。

そうした「α」の画作りは「Xperia」にも活かされていますか?
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 はい。デジタル一眼カメラとスマートフォンのカメラは特にイメージセンサーなどデバイス面が大きく異なっていますが画質面で目指していることは本質的には一緒だと考えています。もちろん、“柱”についてもしっかり共有されており、誇張しすぎない自然なディテールや、人の肌の色や空の青、草木の緑などを人の記憶に忠実に美しく再現することをXperiaのカメラでも追求してきました。
撮影後加工が当たり前になっているスマートフォンのカメラでは珍しい方針ですよね。
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 そうかもしれませんね。ただ、撮った写真をその後に加工・編集する「素材」と考えるのであれば、エッジや色味を過剰に強調したり、ノイズを消しすぎたりした写真はありがたくありません。そのため「Xperia」では、そのまま使ってもきれいで、編集にも適した、ナチュラルな写真を提供したいと考えています。
「α」の各製品は“柱”をベースにそれぞれ個別に味付けされているということですが、「Xperia」については、どのような味付けがされているのでしょうか?
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 高性能なプロセッサーを内蔵するスマートフォンは、一度のシャッターで連続撮影した画像を合成してダイナミックレンジを高めるHDR撮影など、コンピュテーショナル処理の点で大きな強みがあります。「Xperia」の画作りにおいてはそれをどこまで押しだしていくかが議論になりました。結論としては、それはスマートフォンならではの強みなのだから、しっかり活かしていこうということになり、「Xperia」で撮った写真の魅力になったと思っています。具体的にはイメージセンサーの違いが大きい中、コンピュテーショナル処理でノイズ低減やダイナミックレンジ拡大を図り、肌を中心とした色再現やディテール再現については先ほど述べたナチュラルと好ましさの実現を目指して4つのカメラの合わせこみをしています。
-
![[α]カメラ画質設計担当 玉木](./page_assets/images/icon_tamaki.png?rel20240607)
[α]
カメラ画質設計担当
玉木 ちなみにこうしたコンピュテーショナル処理についてはスマートフォンの方が先行していると認識しており、今後は「Xperia」から「α」へのフィードバックも大きくなっていくのではないかなと考えています。
限りなくデジタル一眼カメラの画作りを意識した
「Xperia」
続いては、ここまででお話しいただいた「α」由来の高画質を実現するために、「Xperia」で具体的にどのような処理を行っているのかを教えてください。
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 「Xperia」と「α」では、センサーサイズも異なれば、レンズも異なります。特にスマートフォン搭載カメラ向けの小さなイメージセンサーはノイズ耐性の点で厳しく、暗い場所ではどうしてもノイズを目立たなくするデジタル処理が必要になります。ただ、だからといってノイズを潰しすぎると映像がベタっとした精細感、立体感の損なわれた画になってしまう問題がありました。

昔のスマートフォンで暗い場所を撮った写真を拡大するとびっくりする場合がありますよね。できの悪い塗り絵みたいになってしまうというか。小さい画面で見るならそれでも良いのかもしれませんが……。
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 これに対して「Xperia」では、暗所撮影時になるべくノイズは消すものの、自然に残すような消し方を心がけています。べったりさせず、気持ちの良いサラサラ感を残すと言えば伝わるでしょうか?ソニーは長年のカメラ開発で、どのように画像を処理すれば気持ちのよいノイズ感を残せるのかの知見を蓄積していますから、これをしっかり取り込み画作りに利用しています。暗所撮影時のノイズ感はデジタル一眼カメラとの性能差をはっきり感じられるところで、特に画作りの差異が目につく部分なのですが、「Xperia」であれば「α」で撮った写真と並べてもさほど違いを感じないはずです。
なるほど。ちなみにそれ以外の部分でデジタル一眼カメラとスマートフォンのカメラの画作りが異なりがちなケースってあるのでしょうか?
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 質感の表現、たとえば髪の毛のサラサラ感などはわかりやすいところだと思います。多くのスマートフォンではエッジ強調をかけ過ぎてしまい髪の毛1本1本のエッジが立ちすぎてしまうのですが、「Xperia」では過剰な強調は避けつつ、細かいディテールもしっかり残すような処理を心がけています。
発色についてはいかがでしょうか? ここまでのお話では「α」も「Xperia」も人の肌の色の再現にはかなり力を入れているということでしたが、そもそもなぜ肌の色味が重要なのでしょうか?
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 カメラの被写体で最も大切だと思うのは人物だと思います。そして写真の色味がずれたとき、特に違和感が大きいのが人の肌の色だからです。それ以外の部分、たとえば空の色って少しくらい青が濃くなってもさほど気にならないんですが、肌の色が少し黄色っぽくなるとそれだけでものすごい違和感が生まれるんですよ。そこで「Xperia」では肌の色を自然に、記憶に忠実に再現できるよう「α」の画質を参考にチューニングを行っています。
このあたり、「α」の画作りを担ってきた玉木さんは「Xperia」の画作りをどのように評価していますか?
-
![[α]カメラ画質設計担当 玉木](./page_assets/images/icon_tamaki.png?rel20240607)
[α]
カメラ画質設計担当
玉木 「α」の画質設計を担う立場として、やはりスマートフォン特有の質感の強調みたいなところはずっと気になっていました。パッと見は悪くないのですが、じっと見ているとニセモノのように感じてしまう部分があるんですよね。なので、スマートフォンで写真を撮るときは多少手間でもRAWで撮って、自分で質感や色味を調整していました。その点「Xperia」は、かなりデジタル一眼カメラに近い画作りを行っていて、JPEG撮って出しでも調整の必要のない写真を出力してくれます。「α」で撮った写真と同じアルバムに収めても違和感の少ない仕上がりになると思います。
「α」の哲学を「Xperia」がきちんと再現できているということですね。
-
![[α]カメラ画質設計担当 玉木](./page_assets/images/icon_tamaki.png?rel20240607)
[α]
カメラ画質設計担当
玉木 その通りです。そのほか、先代『Xperia 1 V』に「α」由来の機能として追加された「クリエイティブルック(写真や動画をあらかじめ用意された複数のルックの中から選んで、自分好みの色合いなどに調整して表現できる機能)」なども、ハードウェア的な制約がある中、素晴らしいものに仕上がっていると評価しています。
実は「クリエイティブルック」の中にある「FL」と「IN」はかつて私が「α」のために作りあげたものなんです。これを「Xperia」にも欲しいと言われたときには、機能に込めた熱量も含めてしっかり説明し、私を含め「α」の画質設計メンバーも、かなり深くまで関わるかたちで監修させていただきました。この際、「Xperia」の開発チームがそうした思いに真正面から取り組んでくださったからこそ、ここまでの完成度に仕上げられたのだと思っています。
「α」の技術とノウハウを吸収し、さらに進化した
『Xperia 1 VI』
ここまで、「Xperia」のカメラの画作りについて伺ってきましたが、その最新モデル『Xperia VI』ではどのような画質向上があったのでしょうか?
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 『Xperia 1 VI』では、ここまででお話しした、ソニーの画作りの哲学は大切にしつつ、よりそれを高い次元で実現することを目指しました。画質面では、特に今回は動画の画質がアップしています。これまで以上に逆光時の白とびを抑制できるようになったほか、フルHD撮影時の画質についても内部処理を変更して大幅に改善しています。また、暗い場所についてもノイズリダクション処理の改善により画質アップを実現しました。

レンズもさらにパワフルなものになりましたよね。望遠レンズが85〜170mm相当までの光学ズームに対応したことで、より遠くの被写体を撮影できるようになっています(先代『Xperia 1 V』は85〜125mm相当)。
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 今、運動会などのイベントに行くと、もうほとんどの親御さんがスマートフォンで撮影していますよね。『Xperia 1 VI』なら、かなり遠くの被写体も大きくズームアップして撮っていただけます。また、併せて今回からテレマクロにも対応し、望遠レンズを使ったマクロ撮影が可能になりました。これによって遠くから近くまでカメラとしてのカバレッジを大きく広げたことも『Xperia 1 VI』の大きな進化点と言えるでしょう。
-
![[α]カメラ画質設計担当 玉木](./page_assets/images/icon_tamaki.png?rel20240607)
[α]
カメラ画質設計担当
玉木 「α」で3本ものレンズを持ち運ぶときは、その日に撮影する気持ちがあって、きちんと準備しているケースがほとんどですよね。一方、常にポケットに入っていて、とっさに撮影したい場合にも満足いく写真が撮れるのはスマートフォンならではのアドバンテージだと思っています。

-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 なお、個人的にはこのテレマクロがものすごく気に入っています。小さな被写体をものすごく大きく引き延ばしたように撮影できるのがとても面白いので、ぜひお試しいただきたいですね。花や野菜、果物を撮っただけでも、被写体の瑞々しさが伝わってくるような、これまで撮れなかったような世界が見えてくるはずです。静止画のみならず動画でも使ってみていただけると面白い発見や、新しい映像表現の広がりを感じられると思います。

そのほか、新しい『Xperia 1 VI』で撮影してほしい被写体はありますか?
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 運動会など、被写体が動いているシーンは『Xperia 1 VI』が得意とするところです。今回、カメラが被写体(人間)の骨格情報を元に、人物をより高精度に認識する「姿勢推定技術」を新搭載し、動きが激しかったり、目の前を何かが横切ったりしても、被写体をしっかりとフォーカスし続けてくれるようになりました。
これは、「α」ユーザーならご存じの通り、『α9 III』など最新鋭モデルで実現したばかりの機能です。こうした最新機能を「Xperia」でも実現するため、「α」の開発チームと「Xperia」の開発チームがそれぞれ毎週のように会合をし、緊密な距離感で開発を進めています。もちろん、できあがったプロトタイプはすぐに「α」チームに共有され、そのフィードバックを反映するかたちで機能の精度を高めていきました。

そんなに密にコミュニケーションを取っているのですか?
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 はい。実は「α」と「Xperia」の開発チームは同じビルで働いているので、ちょっとした気になることがあればすぐに聞きに行けてしまうんですよ。雑談レベルであればもっと高頻度にやり取りしているんじゃないでしょうか?
物理的にも近しい距離にいるからこそ、ここまでの統一感を実現できているということなんですね。
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 そうですね。画質については柱となる指標があるため、機能開発のチームほど頻繁なやり取りは行っていませんが、それでも日々、意識のすりあわせは行われていますし、先ほども出たように「クリエイティブルック」や「S-Cinetone for mobile」のような新しい機能が追加されるときはかなり密接にやり取りをしています。このことも「Xperia」のカメラ機能において大きな強みになっていると思っています。
そのほか、『Xperia 1 VI』の新機能で「α」ユーザーに伝えたいものはありますか?
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 『Xperia 1 VI』では、これまで3つに別れていたカメラアプリがリニューアルされ、1つに統合されました。この際、アプリのUIをより「α」に寄せたプロモードを追加しており、「α」の操作に慣れ親しんだ人ほど、違和感なく、スムーズに使いこなせるようにしています。
具体的にどう寄せているのかを教えてください。
-
![[Xperia]カメラ画質設計担当 有山](./page_assets/images/icon_ariyama.png?rel20240607)
[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山 分かりやすいのはファンクションメニューですね。ほぼ「α」のファンクションメニューそのままの見た目と使い勝手を実現しています。また、「α」ではおなじみのフォーカスピーキング表示にも対応します。どこにフォーカスが合っているのかがはっきり分かるので、より撮影ミスを減らせるようになるはずです。フルオートで撮るという方にも、フォーカスも自分でしっかり合わせたいというこだわり派の方にも喜んでいただけるのではないでしょうか。


- α × Xperia
- BRAVIA × Xperia
- Sony Audio × Xperia
- PERFORMANCE & BATTERY
BRAVIA × Xperia

スマートフォンのディスプレイは、写真を撮って確認したり、映画を観たり、メールを読んだり、ゲームをプレイしたり、あらゆる用途に使われる最重要インターフェイスです。であればそれは美しい画質でなければなりません。そこでソニーは「Xperia」のディスプレイに「ブラビア」の映像美を盛り込みました。その最新の取り組みについて、開発に携わったエンジニアたちが語ります。
-
![[BRAVIA]テレビ画質設計担当 高橋](./page_assets/images/icon_takahashi.png?rel20240607)
[BRAVIA]
テレビ画質設計担当
高橋 -
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原
『Xperia 1 VI』は、10年に1度クラスの
大幅画質アップ
まずはこれまで「ブラビア」がテレビとしてどういった画作りを目指してきたのか、その思想とこだわりを聞かせてください。
-
![[BRAVIA]テレビ画質設計担当 高橋](./page_assets/images/icon_takahashi.png?rel20240607)
[BRAVIA]
テレビ画質設計担当
高橋 まず、大前提として映像の世界には、入力された信号を忠実に再現するマスターモニターというプロフェッショナル向けの映像デバイスが存在し、「ブラビア」や「Xperia」にも、その映りを再現する画質モードが用意されています。その上で、最新テレビのパフォーマンスを最大限活かして画作りを行う画質モードも用意されており、ふだん使いにおいてはこちらをご利用いただくようになっています。

「ブラビア」で言うところの[スタンダード]画質モードなどのことですよね。
-
![[BRAVIA]テレビ画質設計担当 高橋](./page_assets/images/icon_takahashi.png?rel20240607)
[BRAVIA]
テレビ画質設計担当
高橋 その通りです。なお一般的に、人は見たままの映像をそのまま再現されると色やコントラストが弱いと感じてしまいがちです。それは人間の脳の特性として、見たものをより明るく、より派手な色で、より美しい情報として記憶してしまうから。そこで「ブラビア」の[スタンダード]画質モードでは、そうした映像のコントラストや質感、発色などを大きく高め、記憶の中のイメージを再現することで、その時の感情の高まりを想起させることをターゲットに映像を作り込んできました。
それに対して「Xperia」のディスプレイがどのように画作りを行ってきたのかも聞かせてください。
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 「Xperia」ではソニーならではの高性能の一端として、10年以上前から「ブラビア」の画質をスマートフォンでも再現することを目指してきました。まずは「ブラビア」の映像エンジンをスマートフォンに落とし込んだ「モバイルブラビアエンジン」の搭載から始まり、「X-Reality for mobile」を経て、2019年に発売した『Xperia 1』では「X1 for mobile」搭載によって、今日までスマートフォントップクラスの映像美を実現し続けています。
なお『Xperia 1』では、先ほど高橋の話にも出たマスターモニターの画質を実現する「クリエイターモード」の実現が大きな目玉になっていたのですが、同時に「スタンダードモード」についても大きく改善しており、当時のブラビアの[スタンダード]画質モードにかなり迫った画質を実現できていたと思っています。
ただ、さすがにそれからもう5年が経過しており、「ブラビア」の画質も認知特性プロセッサー「XR」の登場などによってさらに大きく進化してきています。そこで今回、改めて最新「ブラビア」の画質を「Xperia」に取り込めないかと考え、『Xperia 1 VI』のための新たな映像エンジンの開発に取り組みました。結論から言うと、ディスプレイパネルの大幅刷新も合わせて、この10年で最高の画質向上を実現できたと自信を持っています。

AIの力も借りて「ブラビア」画質を徹底追求
もちろん最後は人の目と手でブラッシュアップ
『Xperia 1 VI』で、改めて最新「ブラビア」の画質を目指すにあたり、具体的にどういうことをやったのでしょうか?
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 今から数年前、次のモデルでやるべきことを模索する中、一度、最新「ブラビア」の映像エンジン(認知特性プロセッサー「XR」)をそのまま「Xperia」につないだらどんな映りになるだろう、そこから何かヒントを得られるのではないかと考えました。

そんなことができるんですね。
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 はい。もちろん大きなものなので内蔵はできないのですが、ケーブルでつないで「Xperia」のディスプレイに表示させることはできますから、高橋さんにお願いして「ブラビア」の開発環境を貸していただき、実際にやってみました。
そこで感じたのは、これまで「Xperia」が目指してきた「ブラビア」の映像美が、実際のものから大きくズレていないということ、しかし、やはり質感や光沢感、立体感など、数値では表現できないような全体的な印象がわずかに異なっているということでした。そして、この違いを再現していくことが、次の「Xperia」で目指すことだという確信を持つことができました。
それを具体的にどのように実現していったのかを聞かせてください。
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 そこが今回とても苦労したところです。最新「ブラビア」に搭載されている高度な映像エンジンをそのままスマートフォンに落とし込むのはサイズ的にも、消費電力的にも現実的ではありません。限られた処理能力でどうやって「ブラビア」画質を実現するのか、いろいろ模索した中で行き着いたのが昨今トレンドにもなっていて技術的にもホットなAIの活用でした。
AIをどのように活用しているのでしょうか?
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 まずベースとなる「ブラビア」の前に、正確に色を記録できる測定器を設置し、その表示性能を機械学習させて「モデル」化します。同様に「Xperia」のディスプレイもモデル化して比較し、差分を埋めていくことで「ブラビア」画質の再現を自動化しています。
色を揃えるだけなら、AIなど使わずとも、測定した「ブラビア」の映像と同じになるよう「Xperia」の色を合わせていくだけでいいのではないのですか?
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 いえ、そんな単純なものではありません。「ブラビア」と「Xperia」のディスプレイはそもそも基本的な性能や特性が異なっていますし、ある部分の色や明るさを変えると他の部分にも影響が及ぶなど、もぐら叩きのような性質もあるためです。
なるほど。そうした特性も込みでモデル化することで、正確な色合わせが可能になるのですね。
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 その通りです。また、最新のディスプレイは10億以上の色を扱えるなど、もはや人間の目と手でどうにかできる範囲を越えてしまっています。しかもそれを確認する人間の目はその日の体調によって見え方が微妙に変わりますし、複数メンバーで作業すると作業者ごとの違いが生じ、結果がぶれてしまう問題もあります。こうした問題もAIを用いることで解消できると考えました。
実際にやってみていかがでしたか?
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 これが予想以上に上手くいきました。単に色を合わせるだけでなく、「ブラビア」ならではの質感や立体感のようなものがうまく再現できていたんです。人間特有の揺らぎやぶれを徹底的に取り除いていくと、ここまで見事に質感まで再現できるのかという気付きを得られましたね。
徹底的に厳密な色合わせが奏功した、と。ただ、これで完成……というわけではないんですよね?
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 そうですね。やはり最後には人の目によるチェックが必要だろうということで、このタイミングで高橋さんら、「ブラビア」の画質設計チームの皆さんにご確認いただくことにしました。
ぜひ、その時の感想を聞かせてください。
-
![[BRAVIA]テレビ画質設計担当 高橋](./page_assets/images/icon_takahashi.png?rel20240607)
[BRAVIA]
テレビ画質設計担当
高橋 第一印象としては、AIでここまで寄るのかとかなり感心しました。ただ、「Xperia」がさまざまなコンテンツを表示するデバイスであると考えたとき、「ブラビア」の[スタンダード]画質モードに揃えた表示は、ホーム画面や写真など、静止画を表示する時にはちょっと鮮やかすぎるかなとも感じました。実際、「ブラビア」でも写真表示時には、やや派手さを抑えたフォトモードに切り替わるようになっていますので、それを取り入れたらよいのではないかと伝えています。
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 これを受けて、静止画のための画質モードを新たに用意しました。そして、動画の部分は[スタンダード]画質モード由来の画質で、静止画やUIの部分はフォトモード由来の画質でと、2つの画質モードを同じ表示の中で共存できるようにしています。
どちらかに切り換えるのではなく、共存できるのはうれしいですね!
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 はい。技術的にも少しハードルが高いところなのですが、そこは妥協しませんでした。また、動画の画質についても、改めて最後に『Xperia 1 VI』開発チーム内でディスカッションし、スマートフォンの画面サイズに最適化した映像になるよう細かくチューニングを行っています。具体的には暗所部分の見え方などを細かく調整し、小さなディスプレイでもしっかり映像の細部まで楽しめるようにしました。
できあがった映像をご覧になってどのように思われましたか?
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 ためしに映画を再生してみたのですが、これまでの「Xperia」と比べて、1枚ベールが剥がれたような、映像がさらに手前に感じられるような立体感、奥行き感を感じられるようになりました。スピーカーが大きく進化したこともあり、使い古された表現かも知れませんが、プライベートシアターにいるかのような感覚で映画鑑賞に没入できました。

『Xperia 1 V』(写真左)と『Xperia 1 VI』(写真右)の画質比較。
『Xperia 1 VI』なら屋外でも
「ブラビア」画質でコンテンツを楽しめる
さて、ここまではいかにして「Xperia」のディスプレイ品質を「ブラビア」に近づけてきたのかというお話を伺いました。しかし、スマートフォンである「Xperia」は、リビングに置かれている「ブラビア」とは根本的に視聴スタイルが異なっていますよね。そうした特性を踏まえた『Xperia 1 VI』ならではの高画質化についてもお聞かせいただけますか?
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 おっしゃる通り、自宅だけでなく、屋外のさまざまな場所で使うスマートフォンでは、どのような環境でもしっかり映像を楽しめるようにする仕組みが必要です。そこで『Xperia 1 VI』では、特に屋外での視認性向上に注力しており、「サンライトビジョン」という新機能を搭載しました。

どういった機能なのか、もう少し詳しく教えてください。
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 そもそも『Xperia 1 VI』では先代モデル『Xperia 1 V』と比べてディスプレイの明るさが約50%向上しています。それによってもともと屋外での視認性が大きく向上しているのですが、さらに映像の暗い部分だけを持ち上げて表示することで、明るい場所でもストレスなく映像を楽しめるようにするという機能が「サンライトビジョン」です。この際、どう明るくするかは、すでに「ブラビア」が持っているノウハウを元に共同で作り込んで行きました。
屋外視聴時に高画質化するためのノウハウが「ブラビア」にあるんですか?
-
![[BRAVIA]テレビ画質設計担当 高橋](./page_assets/images/icon_takahashi.png?rel20240607)
[BRAVIA]
テレビ画質設計担当
高橋 「ブラビア」には、かなり以前から、部屋の明るさや光の色を検知して、リアルタイムに画質を最適化するという機能が搭載されており、それを応用するかたちで、周囲の明るさに応じた暗所の階調調整と色味の補正を行っています。
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 これによって真夏の太陽光下から曇り空、夕暮れまで、さまざまなシチュエーションで映像を細部まで楽しめるようになりました。なお、この機能は動画視聴時のほか、カメラ撮影時やWebブラウジング時などでも利用可能です。
-
![[BRAVIA]テレビ画質設計担当 高橋](./page_assets/images/icon_takahashi.png?rel20240607)
[BRAVIA]
テレビ画質設計担当
高橋 この機能、始めて体験したとき本当に驚かされました。こんなに眩しい場所でこれほど美しい映像を楽しめるのかって。屋外で動画を見ることが多い人にぜひ試してみていただきたいですね。今後は、この開発で得たノウハウを「ブラビア」に還元させていくことも考えています。
そのほか、『Xperia 1 VI』のディスプレイ機能で大きく変わった点はありますか?
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 今回、とても大きな仕様変更としてディスプレイの形状が19.5:9に変更になりました。これまでの21:9ディスプレイと比べてやや横に広がったかたち(縦持ち時)になります。
ユーザー体験的にはそれによってどう変わりますか?
-
![[Xperia]ディスプレイ画質設計担当 松原](./page_assets/images/icon_matsubara.png?rel20240607)
[Xperia]
ディスプレイ
画質設計担当
松原 まず形状の変化によって、YouTubeやSNSなどで一般的な16:9コンテンツを表示したときはこれまでよりも大きく表示されるようになります(横持ち時)。また、シネマスコープサイズ(21:9)の映画コンテンツについてもこれまでとほとんど変わらない大きさでお楽しみいただけます。
なお、『Xperia 1 VI』では画面解像度が4Kから2Kに変更されているのですが、それが従来比1.5倍の輝度アップや低消費電力化に繋がっているため、単純なスペックダウンとは考えていません。解像度が落ちること自体、どうしてもネガティブに受け止められるかもしれませんが、画質というのは解像度だけで決まらず、信号処理や画質エンジンなどトータルの画質設計で決まってきます。スマートフォンの使われ方や求められる性能の変化を踏まえ、今回は2Kにするのがベストだと考えました。

- α × Xperia
- BRAVIA × Xperia
- Sony Audio × Xperia
- PERFORMANCE & BATTERY
Sony Audio × Xperia

何も足さず、何も引かないことを是として、クリエイターの伝えたい音を愚直に伝え続けてきた「ソニーの音」。ここではその音づくりの哲学を長年に渡って磨き上げ、守り続けてきたチーフサウンドデザイナー・加来が、『Xperia 1 VI』の音をレビューします。
-
![[Sony Audio]音質設計担当 加来](./page_assets/images/icon_kaku.png?rel20240607)
[Sony Audio]
音質設計担当
加来 -
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本
『Xperia 1 VI』の音は
「他人じゃない」
まずはソニーの音作りがどういったものなのかを教えていただけますか?
-
![[Sony Audio]音質設計担当 加来](./page_assets/images/icon_kaku.png?rel20240607)
[Sony Audio]
音質設計担当
加来 私たちソニーグループには、ソニー・ピクチャーズエンタテインメントや、ソニー・ミュージックエンタテインメントといった仲間がおり、日々、密接に連携を取りながら、製品作りに取り組んでいます。そうした中、ソニーが音作りのテーマとしているのは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」の旗のもと、クリエイターが考えるファンに届けたい音を具現化することです。

それはどんな音なのでしょうか?
-
![[Sony Audio]音質設計担当 加来](./page_assets/images/icon_kaku.png?rel20240607)
[Sony Audio]
音質設計担当
加来 映画で言うとダイアログ(セリフ)、音楽で言うとボーカルを大切にするということです。この音をしっかり伝えるべく、それぞれの音響設計担当者が、日々、クリエイターとやり取りしながら、時には制作現場で実際にどのような音作りをしているのかも見させていただきつつ、少しずつ、地道に理解を深め、製品の音に落とし込んでいくということをやってきました。私はそうした中で、それぞれの担当者が作りたい、目指している音を尊重しつつ、バラバラの方向に向かってしまわないように、旗振りをして方針を統一するという仕事をやっています。
それはソニーのあらゆるオーディオ製品において、ということでしょうか?
-
![[Sony Audio]音質設計担当 加来](./page_assets/images/icon_kaku.png?rel20240607)
[Sony Audio]
音質設計担当
加来 いえ、私が担当しているのはスピーカーやサウンドバーなど、ホームオーディオ、ホームシアター機器となります。ウォークマンなど他の分野には別の旗振り役がいます。
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 ただ、それぞれのチーフにはかなり密接な繋がりがあり、部門によって全く異なる音を目指しているということはありません。と言うか、ソニーの中で良い音を追求していると、いつの間にか「ソニーの音」になっていくんですよ。
それはなぜなのでしょうか?
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 冒頭のお話にもあったよう、グループ内に多くのクリエイターやエンジニアがいることが大きいのだと思っています。その一方で自分自身、熱心な映画ファン、音楽ファンでもありますから、結果として自分の中に「コミュニティ・オブ・インタレスト(クリエイターからエンジニア、リスナーまで、共通の感動体験を共有する人たちの集まり)」が凝縮されたかたちで醸成され、自然とそうしたクリエイターの思いをリスナーにそのまま伝えるような音作りに行き着くのかもしれません。
それが「ソニーの音」なんですね。
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 はい。クリエイターの伝えたいことは、もう作品の中に含まれていますから、僕らが勝手に変えたり、何かを増やしてあげる必要はないんです。僕らは何も足さないし、何も引かない。だから自然と同じ音になっていくんです。
なるほど。では、それを踏まえた上で、今回『Xperia 1 VI』でどのような音を目指したのかを教えてください。
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 今回、加来が目の前にいるから言うわけではないのですが(笑)、『Xperia 1 VI』では、加来の担当したプロダクトのエッセンスをそのまま落とし込んだような音を目指しました。映画を観ている時にはサウンドバー『BRAVIA Theatre Bar 9』の包み込まれるような立体音響空間が、音楽を聴く時にはSignature Seriesのニアフィールドパワードスピーカー『SA-Z1』の怪物級の立体的なミュージックステージが手のひらに乗っているかのような体験を、可能な限り、限界を決めずに再現してみよう、と。これが自分にとって最高の体験だと思っているので、素直にそこを目指そうということです。
加来さんはその話を聞いてどう思われました?
-
![[Sony Audio]音質設計担当 加来](./page_assets/images/icon_kaku.png?rel20240607)
[Sony Audio]
音質設計担当
加来 あまり社内でそういう照れくさい話はしないんですけども(笑)、はじめて『Xperia 1 VI』の音を聴いた時、「他人の音じゃないな」と素直に思いました。さきほど、クリエイターの思いをリスナーにそのまま伝える音作りをしていくと、いつの間にか「ソニーの音」になっていくという話がありましたけど、まさにこれがそういうことなんでしょうね。
『Xperia 1 VI』は内蔵スピーカーが大幅進化
特にアニソンは必聴!?
今回、『Xperia 1 VI』では、内蔵スピーカーの音質が飛躍的に向上したとお聞きしました。具体的にどのように進化したのかを教えていただけますか?
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 その前に、まずスマートフォンの内蔵スピーカーが抱えている構造的な難しさについて説明させてください。一般的なステレオスピーカーでは左右のスピーカーは同じものを使い、左右対称に配置されるのが当たり前ですが、スマートフォンではその当たり前がまず実現できません。どうしてもカメラやUSBポート、バッテリーなどを避けた位置に配置せざるを得ず、しかも小指の先くらいのスピーカーしか入れられません。そのため、どうしても音域が狭かったり、左右の音の聞こえが変わってしまったりする問題があります。
「Xperia」ではこうした振幅特性、位相特性のズレといった音響上の課題を、ソニーが長年培ってきた信号処理技術で徹底的に整えるところからはじめています。これをほどほどのレベルで妥協してしまうと、その後なにをやっても良い音にならないんです。

「Xperia」はそこをしっかりやっている、と。
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 その通りです。もちろん、それができるのはソニーが長年、オーディオ機器の開発に取り組んできたから。気がつきにくいところなのですが、そこにかなりのノウハウとテクノロジーが盛り込まれているんですよ。
なるほど。その点で今回、何かアップデートされていることはありますか?
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 はい。とても大きなアップデートとして、音の根幹を担うスピーカーユニットを新設計しました。一般的にここまで小さなスピーカーでは低い音がほとんど出せないため、信号処理で音量を増幅する必要があります。この際、従来のスピーカーでは歪みが大きくなってしまい、音質がかなり損なわれてしまっていたのですが、『Xperia 1 VI』の新しいスピーカーは大振幅でも歪みが小さいため、その後の信号処理も攻めたチューニングが可能になり、声や楽器の豊かさなど、低音の再現性が劇的に向上しています。
ポテンシャルの上がったスピーカーを活かしきるようにチューニングも改善しているので、沈み込むような低音からはじけるような高音まで、音のコントラストも大きく改善され、それによってより生々しさを感じられるようにもなりました。
-
![[Sony Audio]音質設計担当 加来](./page_assets/images/icon_kaku.png?rel20240607)
[Sony Audio]
音質設計担当
加来 「Xperia」の内蔵スピーカーは過去モデルも素晴らしい完成度だったと思うのですが、実際に最新の『Xperia 1 VI』と聴き比べると全然違って感じますね。実際のスピーカー位置よりも広がり感がありつつ、スマートフォンの中に小人がいて歌っているように感じられるというか。確かにとても生々しく感じます。
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 加来さんにそう言っていただけるのはうれしいですね。『Xperia 1 VI』では、喉から出ている音だけでなく、その周辺、胸腔で響かせるチェストボイスも加わったリッチな音を再現できたと思っています。

そうした『Xperia 1 VI』の高音質化の恩恵を受けやすい音楽ジャンルがありましたら教えてください。
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 ずばりアニソンですね。実はアニソンってものすごくハードルの高いコンテンツなんですよ。同時に複数のトラックがものすごいスピードで音の粒をばらまく中にボーカルがいて……。それをしっかり分離させて、クリアにバランス良く聴かせるのは本当に大変なんです。このバランスが少しでも崩れると、クリエイターがノリよく重ねていった音の気持ちよいアンサンブルが一気に崩れてしまって、聴くにたえないものになってしまいます。
その点、『Xperia 1 VI』のスピーカーなら、今どきのアニソンもしっかり、気持ちよい音で再生できます。もちろん、ポップスもロックもジャズもクラシックも、目の前に小さなステージが出来上がるような臨場感で楽しめますので、ふだん、スピーカーで音楽を再生しないという方にも聴いてみていただきたいですね。
ちなみにヘッドホンの音質はいかがでしょうか?
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 もちろん、スピーカー同様、従来モデルよりもさらに良い音にすべく、さまざまな点を見直し、音質向上させています。特に今回は有線ヘッドホンの音質がかなり良くなりました。アンプからヘッドホンジャックに至る経路を徹底的に音質重視で見直しまして、特にハイレゾ音源の持つ空気感、広がり感をより堪能していただけるようになっています。また、DACやアンプの性能を向上させたことで、よりクリアで厚みのある音になっているので、同じヘッドホンでもワンランク上の製品に交換したくらい違って聴こえるはずです。ワイヤレスヘッドホンについても劇的な改善ではないものの、基板設計の見直しなどが高音質化に貢献しています。

手のひらに乗る、自分だけの
プライベートシアターサウンド
ここまで主に音楽再生について伺ってきましたが、映画のサウンドについてはいかがでしょうか? 映画にも今どきの流行りみたいなものはあるのですか?
-
![[Sony Audio]音質設計担当 加来](./page_assets/images/icon_kaku.png?rel20240607)
[Sony Audio]
音質設計担当
加来 そこはやはり立体音響でしょうね。最近はDolby Atmosのような立体音響フォーマットで作られた作品がとても増えており、しかも動画配信サービスなどで気軽に楽しめるようになりました。結果として、それまでの映画と比べて、画面の外で鳴っている音がものすごく増えていて、それが分からないと作品に十分に没入できないようにもなってきています。この傾向は今後、どんどん加速していくはずです。
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 そうした中、「Xperia」では早い段階からDolby Atmosなどの立体音響フォーマットに対応しており、内蔵スピーカーでもヘッドホンでも立体的なサウンドを楽しめるようにしてきました。
その上で、今回特に推したいのはやはりスピーカーによる再生です。先ほどお話しした、スピーカー性能の向上によって、立体音響もよりリアルに、より迫力が増して、映画館の様な臨場感を感じていただけると思うので、ソファやベッドに寝転んだりしながら、自分だけのプライベートシアター感覚で映画を楽しんでいただければなと思っています。

その際の音作りにおいて、どんなことにこだわりましたか?
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 スマートフォンでの映画鑑賞は、どうしたってブラビアとサウンドバーを組み合わせた体験にはスケール感の点で及ばないところがあります。画面なんか比べものにならないくらい小さいですからね。でも、視聴距離はずっと近いので、体感としては55V型くらいのテレビで見ているのとさほど変わらない感覚で楽しめるんですよ。ただ、だからといって大型テレビ向けサウンドバーのようなスケールのサウンドを再現するといったことはしていません。そもそもできないというのもありますが、もちろんそれだけではないんです。
-
![[Sony Audio]音質設計担当 加来](./page_assets/images/icon_kaku.png?rel20240607)
[Sony Audio]
音質設計担当
加来 我々は画面サイズに合った音を出すことが、映画への没入感を増すためにとても重要なことだと考えています。映画館のスクリーンと大型テレビ、そしてスマートフォンの画面では、それぞれ画面サイズが異なりますから、適切な音質だったり、画面と違和感のない音像のサイズだったりが異なっているんです。10m先にある巨大な映画館のスクリーンに写されている大きな顔から出ている声と、手元のスマートフォンに映されている小さな顔から出ている声が同じ音のわけがありませんよね。

確かに、スマートフォンの小さな画面で見ているのに、映画館のような響く音で聴こえてくると違和感がありますね。
-
![[Xperia]音質設計担当 松本](./page_assets/images/icon_matsumoto.png?rel20240607)
[Xperia]
音質設計担当
松本 ですので、『Xperia 1 VI』では、映画館の空間をギュッと小さくして、その中で音の立体感やシーンの雰囲気をしっかり感じられるような音作りを心がけています。ヘッドホンで視聴するのと比べて耳疲れも抑えられますので、映画やドラマをじっくり楽しんでいただけますよ。

- α × Xperia
- BRAVIA × Xperia
- Sony Audio × Xperia
- PERFORMANCE & BATTERY
PERFORMANCE & BATTERY

ここまでで『Xperia 1 VI』に組み込まれた、さまざまなソニー製品由来の技術やノウハウについて紹介してきました。最後のこのパートでは、その高性能を快適に、安定して長時間使えるようにするためのパフォーマンス最適化について、その専任チームのメンバーたちに話を訊きます。
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 -

ソフトウェア
設計担当
大木
パフォーマンスの最適化の専任チームが
『Xperia 1 VI』を徹底チューニング
『Xperia 1 VI』は、スマートフォン最高クラスの処理性能を誇るSoC(CPUなど、さまざまな機能を統合した半導体チップ)「Snapdragon 8 Gen 3」搭載など、フラッグシップモデルならではのリッチなスペックを誇ります。その高性能を引き出すため、どのような取り組みを行っているのか聞かせてください。
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 体感パフォーマンスを高め、しかも安定して長時間動作できるよう、局所的な最適化ではなく、ハードウェアからソフトウェアまでスマートフォン全体を俯瞰したチューニングを行いました。スペックや高性能だけを追い求めた最適化は、消費電力が高くなることで、発熱やバッテリーもちに悪影響が出てしまうため、ソニーではかねてよりシステム全体でのパフォーマンス最適化を重視しています。『Xperia 1 VI』でも、「パフォーマンスエンジニア」である私を含む専任チームが、スペックでは測りきれない高性能化を追求しています。

そうした『Xperia 1 VI』ならではのチューニングを実感できる利用シーンにはどんなものがありますか?
-

ソフトウェア
設計担当
大木 分かりやすいところでは4K 120fpsでの動画撮影がとりわけシステム負荷が高く、消費電力が大きくなり、発熱しやすいユースケースですね。『Xperia 1 VI』ではそうした多くの利用シーンでも、可能な限り触れないほど熱くなってしまったり、強制停止したりしないようにしています。
具体的にはどういったことをやっているのですか?
-

ソフトウェア
設計担当
大木 さまざまなシチュエーションでCPUなどシステム上の動作を解析し、必要な処理だけにCPUのリソースを割り振ることで無駄な消費電力と発熱を抑える取り組みを、本当に細かなレベルまで徹底してやっています。
この際、最優先したのは、ストレージの許す限り録画し続けられること。録画に失敗したり、中断したりすることで撮影機会が失われてしまうことだけはあってはなりませんから。そのリスクを極小にするべく、それでもなおシステムにかかる負荷が一定以上に高まってしまった場合は、極力撮影体験に影響を及ぼさない範囲で撮影機能に制限をかけるなどしています。
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 こうした工夫は4K 120fps撮影に限らず、さまざまな利用シーンで行っており、たとえばカメラを使うさまざまなアプリについて、快適さを損なわない範囲で消費電力や発熱をギリギリまで削っていくチューニングを行っています。

薄皮をそぎ落とすように無駄をカットしていくことで、長時間、安定したパフォーマンスを発揮できるようにしているのですね。
-

ソフトウェア
設計担当
大木 その通りです。一方、アプリの起動時などは、あえてパフォーマンスを上げて即立ち上がるようにもしています。
ただ起動させるだけの部分にチューニングの余地なんてあるのですか?
-

ソフトウェア
設計担当
大木 実はパーツメーカーから提供されているコード(プログラム)やOS標準のコードは、一定のマージンを取った作りになっていて、そのままにしておくと本来のパフォーマンスを使いきれないところがあるんです。ただ、アプリの起動は全てのユーザーがかなり高頻度に行う動作ですから、少しでも速い方がいいですよね。本体内の温度が上がりすぎないようしっかり監視しつつ、CPUのパフォーマンスが最大まで出るようにしてサッとアプリが起動するようにしています。
発熱を抑え、効率的に放熱する
先進のハードウェア設計
ここまでのお話で、『Xperia 1 VI』が発熱しすぎないよう巧みに制御されていることが理解できたのですが、それでもやはり熱を効率的に逃がす仕組みは重要ですよね。このあたり『Xperia 1 VI』がどのような構造的対策を行っているのかを聞かせてください。
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 まず「Xperia 1」シリーズとして初めて「ベイパーチャンバー」というCPUやカメラが発する高熱を拡散し、外部に放熱しやすいようにしてくれる熱拡散装置を搭載しています。これによって内部に熱がこもることがなくなり、安定したパフォーマンスを長時間発揮できるようになりました。

-

パフォーマンス
エンジニア
春木 今回の新しいカメラ構成は、構造上の変化により放熱性能が厳しくなっているのですが、ベイパーチャンバーを搭載したことで十分な放熱性能を維持することができています。もちろん、ただベイパーチャンバーを載せればいいというものではなく、長年培ってきたスマートフォンの熱設計のノウハウを結集して、部品の選定・内部構造の最適化を行うことで、サイズ・重量を損なわずに放熱性能を最大限に発揮することができました。

ベイパーチャンバー以外の対策についても教えてください。
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 新たなカメラ構成は構造だけでなく消費電力も不利な条件があるのですが、SoCやディスプレイの消費電力が改善できたため、同一条件下では、「Xperia 1」シリーズとして最も省電力になっています。省電力は発熱の低減にも直結しますから、最高の熱対策と言えるでしょう。
今回、ディスプレイの解像度が4Kから2Kになっていますが、その点も省電力に効いていそうですね。
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 非常に大きいですね。また、ディスプレイの材料も最新ですから、屋外での撮影時など画面を明るくした際の電力効率も改善されています。これによって、屋外で見やすくなったことに加え、同じ明るさであれば、従来機種より省電力になっているんですよ。
それはすごい。これからの暑いシーズンにも安心して使えそうですね。
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 はい。『Xperia 1 VI』は消費電力的にも構造的にも改善を入れて、「Xperia 1」シリーズとしては過去最高と断言できる放熱性能を実現し、パフォーマンス向上と長時間利用を両立しました。過去の製品では、お客さまから厳しい声をいただくこともありましたが、『Xperia 1 VI』では必ずやご満足いただけると自信を持っています。
「Xperia」史上最長駆動&寿命を実現した
“感動”バッテリー
どんなに優れたスマートフォンでも電源が切れてしまったのでは意味がありません。特にハイエンドモデルは消費電力が大きいイメージですが『Xperia 1 VI』はどれくらい長時間使い続けられるのでしょうか?
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 Xperia 1 VIはバッテリー容量5000mAhをそのままに、消費電力を大幅に減らすことで、ヘビーユーザーでも丸2日使えるバッテリーもちを実現しました。
Xperiaユーザーの調査をしたところ、ヘビーユーザーは約6時間もスマートフォンに触っていることがわかっており、そういったユーザーでも、丸2日使っていただけるくらいのバッテリーもちを中長期的な目標に掲げて開発を進めてきました。
ハイエンドの「Xperia 1」シリーズでは、先代の「Xperia 1 V」で約1.7日ともう少しのところまできていましたが、「Xperia 1 VI」では、特にディスプレイの消費電力が改善されたことで、目標を達成するだけでなく、「Xperia」史上最高のバッテリーもちを実現しています。
ディスプレイについては、先ほどお話した、解像度や材料に加えて、可変リフレッシュレート対応も効果がありました。

可変リフレッシュレートとはどういった機能なのですか?
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 利用シーンに応じてディスプレイのリフレッシュレート(1秒間あたりの書き換え回数)を1Hz〜120Hzまで動的に変更できるというものです。特に静止画表示時などは1Hzまでリフレッシュレートを落とせるため、大幅に消費電力を減らせます。ウェブやSNSの閲覧中は静止画表示状態も多いため、消費電力を20〜30%ほど削減することができました。動画やゲームなども、コンテンツに最適なリフレッシュレートに調整しますので、パフォーマンスと省電力を両立できます。
そうした新機能もあって念願のバッテリー性能を実現できたのですね。
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 「Xperia」ではさまざまなスペックについて、これならユーザーが感動してくれるだろうという数値を目標に設計しています。バッテリーについては「丸2日」が感動していただけるレベルだろうと考え取り組んできたので、実現できたことは本当にうれしく思っています。
-

ソフトウェア
設計担当
大木 この数値を実現するべく、パフォーマンスエンジニアたちが試作機を日常の中で長期間試用し、なにをすると電力を消費するのか、いつの間にかバッテリーが激減している時には何が起きているのかなどを徹底的にチェック。実使用で浮かび上がってくるバッテリーを無駄に消費する要因をひとつひとつ潰していきました。本当にもうこれ以上、消費電力を最適化できないというところまで追い込んだ自負がありますし、エンジニアとしてとても感動しています。
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 そしてもうひとつ「Xperia」過去最高のバッテリーを謳える要素として、従来モデルでも好評な「3年使い続けても劣化しにくい長寿命バッテリー」を4年にまで延ばすことに成功しています。
その実現にはどのような難しさがあるのでしょうか?
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 デザイン・サイズにもこだわっている「Xperia」には、高電力密度のバッテリーを採用していますが、充電速度や寿命が犠牲になってしまいがちという課題がありました。そうした中、我々はバッテリーメーカーと密にやり取りしながら、高電力密度でありながら充電速度を損なわず、バッテリーの素材や利用状況に応じた充電アルゴリズムの開発に挑戦し続けてきました。今回、その改良を積み重ねて、ついに4年もつものを作れるようになったということです。しかも、充電速度も『Xperia 1 V』から若干速くなっています。
ハイエンドスマートフォンは高額な製品ですから長く使えるのはうれしいですね。
-

パフォーマンス
エンジニア
春木 はい。新素材を採用するだけでなく、新素材に最適化した充電アルゴリズムを開発することで、4年長寿命を実現しつつ、充電速度も若干改善することができました。ちなみに1年、2年の使用でも劣化の進行をおさえていますので、買い替えサイクルの早いコアなスマートフォンユーザーの皆さんにとってもメリットのある改善だと考えています。





![テレビ ブラビア[個人向け]](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia.jpg)
![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg?v=20180319)

















![[法人向け] パーソナルオーディオ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/personal_audio_biz.jpg)






![[法人向け]カメラ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/camera_biz.jpg)






![[法人向け] Xperia™ スマートフォン](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/xperia-biz.jpg)
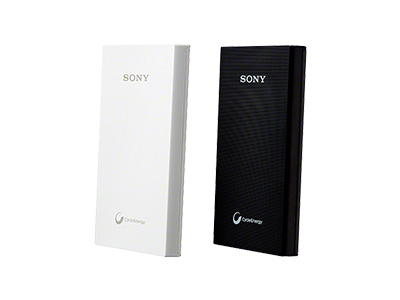

![[法人向け] aibo](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/aibo_biz.jpg)







![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg)
![[法人向け] デジタルペーパー](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/digital-paper.jpg)





















































[Xperia]
カメラ画質設計担当
有山
写真の色味がずれたとき、特に違和感が大きいのが人の肌の色なんです。そこで「Xperia」では肌の色を自然に、忠実に再現できるよう「α」の画質を参考にチューニングを行っています。また、ノイズも気持ち良いサラサラ感を残すように心がけています。